塩のことわざ・慣用句
製塩方法の歴史的な変化
塩の近代史メモ
昔の塩と今の塩
|
 |
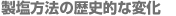 |
|
製塩の歴史の簡単なことはホームページ「日本の塩」に記載しました。昔の塩についての質問が多いので補足説明をします。
日本の塩は昔から海水を濃くする工程(採かん)と、煮詰めて塩をとる工程(煎ごう)に分かれています。いつの時代に行なわれていたかを製塩法の変遷として図に書いてみました。
藻塩焼きは歌にもうたわれ、現在はその再現を観光や商売の宣伝に使っているところもあり大変有名です。しかしも塩焼きを実際にどのような方法で行なったかは分かりません。こういう方法だったに違いないという議論はたくさんあって百人百様です。私の思う藻塩焼きがそれぞれあって、あたかも邪馬台国論争のようなものです。自然浜も本当のことはわからないのです。
揚浜塩田は地域によりいろいろな方法がありますが、塗り浜方式の揚浜塩田が能登半島珠洲市に残っており、夏季の観光シーズンは稼動しています。入浜塩田は赤穂市海洋科学館、香川県宇多津町産業資料館、山口県三田尻塩田記念産業公園、などで復元されており、塩作り体験などができます。流下式塩田やそれに付帯した枝条架濃縮は赤穂海浜公園でややミニチュアだが稼動している。膜濃縮は現在の製塩方式で、全国6工場で稼動中であり、予め連絡すれば見学できる。連絡先リンクしているホームページ「日本の塩」の「塩はどこで作られているの」のコーナーを見てください。
このような採かん方法の改革によって、生産性が上がり、苛酷な労働から解放された。どのくらい生産が合理化されたかの一つの指標として生産効率の変化を表に示している。
土器製塩は多くの博物館で展示されている。石釜は残っていない。鉄製の平釜は古くは宮城県塩釜神社の御釜屋に4基ある。釜形式は古い平板型から、やや深くなり、さらに蓋がついた蒸気利用式平釜(昭和35年頃になくなった)に変化してきた。フレーク塩や凝集晶の塩を作るためにオープンタイプ、クローズタイプそれぞれに形式が若干異なるさまざまなものが使われている。真空式は大規模生産に現在使われている縦型の釜でサイコロ型の結晶の塩ができる。
生産効率の変化
| |
面積当たり
(t/ha/年) |
労働生産性
(人/千t) |
概算コスト
(万円/t) |
| 揚浜塩田 |
70 |
1,600 |
- |
| 入浜塩田 |
110 |
70 |
20 |
| 流下式塩田 |
250 |
2.5 |
4 |
| 膜濃縮 |
1,000,000 |
0.2 |
1 |
|
|
|
|
|
 |