塩味の常識
(2010記載)
塩のソムリエに
チャレンジ(2010記載)
高価な塩が
よい塩ではない
安全な塩を簡単に
見分ける方法
塩味の特徴
塩の上手な選び方
ユーザーのための
塩学入門
塩の賞味期限
漬物に使う塩
駐車場の凍結防止
|
| |
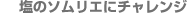 (2010記載) (2010記載) |
 |
 |
 |
最近、塩のソムリエ制度を検討したい。というご意見を伺った。塩の味が分かる人の認定制度ということらしい。一体どのような条件を満たせばソムリエといえるのだろうか。ワインのソムリエでは、知識、味覚、接客の3条件が求められるが、塩で期待しているのは味覚であるらしい。確かに塩の味見の方法は確立していない。著者がやっている味の違いの有無の判定方法を紹介して参考に供したい。興味がある方はチャレンジしてみましょう。塩の味見で大切なことは、味は先入観で支配されるから先入観がない状態で味見をしなければならないこと。塩は食べるものでなく調味料なので調味料として使った味でなければならないこと。ワインのように直接飲んで味見をしても意味がないことが難しい点である。
塩はその結晶を見れば少し勉強した人ならその製法など塩特性はわかる。塩を直接舐めては先入観を与えて味見している状態だし、調味料としての使うという、塩本来の使い方からも外れている。
■味見
下準備
塩を5−10種類選ぶ。この5種の塩から3種を選んで味を見ていただきます。
玉ねぎを水1.5リットルにつき1個ざく切りで加える。
30分弱火でゆっくり煮沸してスープをこし取り、蓋をして放冷。
テスト対象とする塩3種(A,B,C)を、スープ中の塩化ナトリウムが0.8%になるように正確に計りとる。(水分や「にがり」分を正確に補正する。後述注意を参照)
スープを重量で一定量計りとり、塩化ナトリウムが同一(0.8%)になるように塩を加えて溶かし、試料A,B,Cのスープを作る。
1.塩ソムリエ名人級(塩の種類やブランドが分かる)
(1)選ばれた5-10種類の塩を皿などに出して味見してもらい確認する。全く事前確認等の情報なしで種類やブランドが分かる人はまだ見たことがない。もしいれば大変な名人ソムリエです。
(2)記入表を配る
| A |
氏名 |
正答数 |
| 回 |
番号 |
回答 |
メモ |
正誤 |
| |
A |
|
|
|
| 1 |
B |
|
|
|
| |
C |
|
|
|
| |
D |
|
|
|
| 2 |
E |
|
|
|
| |
F |
|
|
|
(3)小カップに30〜50mlづつ注ぎ分ける。被験者は記入表に回答を書きこむ。
同一サンプルで順番を変えて配る。被験者は記入表に回答を書きこむ。
判定
記入表の正答数が6点中4点以上ならば塩味ソムリエといえるのではないだろうかと考えています。回答、メモの内容が同一資料であまりに違うときはマイナス1点とする。
2.塩ソムリエ入門級(塩味に差があることが分かる。塩の味の差の有無の検定にも使う)
(1)選ばれた塩3種を皿などに出し、味見をしてもらい確認する。配ったスープ3点のうち2点は同じ塩で1点だけが違っています。どのカップが違う塩ですか書いてください。テストは3回行います。回答を見る、人の意見を聞く、はしないでください。という説明をする。
(2)記入表を配る
| B |
氏名 |
正答数 |
| 回 |
番号 |
違うのはどれ |
メモ |
正誤 |
| |
A |
|
|
|
| 1 |
B |
|
|
|
| |
C |
|
|
|
| |
D |
|
|
|
| 2 |
E |
|
|
|
| |
F |
|
|
|
| |
G |
|
|
|
| 3 |
H |
|
|
|
| |
I |
|
|
|
(3)同一スープ2点、違うスープ1点、の組み合わせを3つ作り、どのスープが違う味かを記入する。3回とも正解であれば味の差が判別できたとする。(味見しなくても1/3は当たりますから、3回当たらなければ正解にはしません)
判定
塩ソムリエ入門級、正解だった人については塩味の差が分かる塩ソムリエ入門級としてよいのではないかと考えています。差が分かれば後は練習すればソムリエになれる可能性がありますが、ここで正解にならないようならソムリエとしての素質はないからあきらめた方がよいでしょう。
3.塩味の差の検定(塩そのものが多くの人に分かるものかどうかの判定、すなわち個人の差ではなく塩に差があるかどうかの判定をします)
塩ソムリエ入門級のテストを10人単位で行います。
10人中5人まで味の差を判別できた。
判定:2つの塩には味の差がある可能性が高い。
10人中8人は味に差があると判別できなかった。
判定:2つの塩にはほとんど味の差がない可能性が高い。
10人中一人も味の差を判別できなかった。
判定:2つの塩には味の差はないと判定してよい。
■注意
・どの試料が何という塩か、味の特徴はどうかなど、事前に情報を入れると味見テストにはならない。人間の味覚は事前の情報で大きく左右されるものである。
・塩の選び方では、似た者同士では難しい。味の違いを強調している塩で試すほうが分かりやすいが、ソムリエは微妙な塩の差を判定することを考えているようなのでそんな配慮は炒らないという考えもある。
・塩化ナトリウム濃度を一定にしなければほとんど意味のないテストになる。塩分濃度に対する感度は味の感度に比べてはるかに感度がよいのが普通なので正しく計ることが大切。例えば、塩化ナトリウムを0.8%にしたい場合の簡単な計算方法は、裏面の栄養成分表示で100g中のナトリウム32gならば、塩化ナトリウムは32×2.54=81.28g、スープ中の塩化ナトリウムを0.8%にするにはスープ100gに対し、0.8×100/81.28=0.984gを正しく計りとって加えるとよい。
・テストの素材にはスープを使っているが、いわゆる具が入ってはいけない。具が入ると塩分の浸透・拡散等の問題が絡んで同一の試験資料にすることが困難になる。
低ナトリウム塩では塩化ナトリウム+塩化カリウム合量で同じにするとよい。
・このテストで味が分からなかったからといってがっかりすることはない。どのテストも難しい。わからないのは普通であり、味覚異常ではない。
・味の差がないと判断されても、塩として差がないということではない。調理の中の塩の使い方はきわめて変化に富み、味だけでは決まらない。料理の味は調理の使い勝手や素材との相性など非常に多くの要素で決まるものである。ここでソムリエテストというのは塩の味だけに焦点をおいたテスト方法であることを忘れてはいけない。また、味に差がないという判断でも、味に対する感度は個人差があることを配慮しなくてはならない。一般人のおおよその目安を示すものである。
|
 |
|
|
 |